授業改善に関する教員研修
8月28日に中高教員研修を実施しました。
今回のテーマは「観点別評価を通じた授業改善」です。今年の3月にも観点別学習状況の評価について研修を実施したところですが、今回は評価の方法を踏まえて従来の授業をどのようにブラッシュアップし、よりよい授業につなげていくことができるかという点に注目しました。
はじめにシラバス作成の担当者より、シラバスの公開日程およびシラバスの意義に関して説明がありました。本校では昨年度よりシラバスの試行導入を行い、本年度から本格的に導入しています。すでに多くの学校においても導入されているところではありますが、本校の場合には「何を・どのように学ぶか」という点に特化し、あわせて授業を通じて教員が何を伝えようとしているのか、ということを伝えていくことを主眼としたシラバスの構築をすすめています。教員にとっても、生徒にとっても望ましいシラバスとは何か、今後も改善を重ねていきたいと思います。
続いてシラバスや観点別評価を踏まえた授業改善について、明治学院大学心理学部助教の越智拓也氏による事例報告がありました。越智氏は昨年度まで本校教諭として勤務しており、教科教育学の知見を踏まえつつ本校での実践事例を述べ、改善の具体的方法について解説しました。
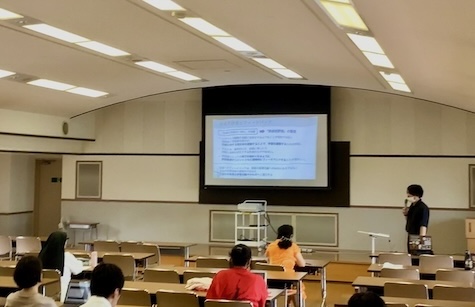
その後、教科をまたいだ複数のグループに分かれて、シラバスや観点別評価に関する実践事例を共有しました。他教科の事例は、教科ごとの研修や実践事例の研究においてはなかなか触れることが難しいものです。一方で、授業方法をよりよいものにしていく鍵が教科横断的な視点から得られることも少なくありません。とりわけ本校のような小さな学校では、教科の枠を超えての交流も一つの強みになるように思います。

最後に校長先生より2学期の指針についてお話があり、研修は終了しました。教育における不易と流行の双方に注目しながら、よりよい学びの実現にむけて努力を重ねていきたいと思います。